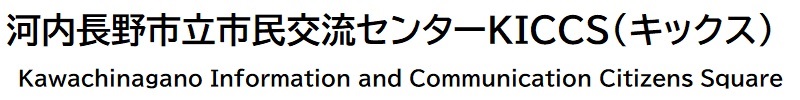本文
【ブログ】くろまろ塾 歴史編 観たくなる奈良の仏像
くろまろ塾 教養講座 歴史編 すごいぞ!レプリカ
第1回目「観たくなる奈良の仏像」

皆さん、こんにちは。くろまろ塾運営ボランティアの西岡です。
今日は、連続講座「教養講座 歴史編 すごいぞ!レプリカ」の1回目「観たくなる奈良の仏像」を受講しましたので、レポートします。

講師の奈良県立大学地域創造学部教授 山田 修さんは、民間企業にて文化財の3Dデジタル化、映像・V Rコンテンツ制作に従事されたのち2009年より東京藝術大学大学院にて仏像の3Dデータを用いた保存修復や模刻に関する教育研究をされ、2021年より奈良県立大学にてデジタル技術を用いた文化財の活用方法について研究を行っていらっしゃいます。

日本における都道府県別国宝の所有数は、1位東京、2位京都、3位奈良とのこと、京都は分かるとしても東京が1位とは意外でした。その理由は東京の所有する国宝のほとんどが東京国立博物館にあるからとのことでした。ところが彫刻に絞ってみると、奈良が断トツの76件、2位は京都の41件、3位は大阪と和歌山の5件ずつでした。しかもこれらは博物館ではなく、それぞれのお寺などで維持保管されているものが多いということでした。
仏像の制作について、材質別に分類すると(1)銅の合金でつくられた銅造(2)土でできた塑造(3)乾漆造(脱活乾漆)(4)乾漆造(木心乾漆)(4)木造(一木造り)(5)木造(寄木造り)などが紹介されました。銅合金の鋳造や寄木造りなどの制作過程は、難しいけれど想像できなくないですが、耳慣れない「脱活乾漆」造りの仏像制作の過程を紹介頂きました。代表作としては、阿修羅像をはじめとする興福寺の八部衆があります。特徴は張り子のような作りなのですが、異なるのは、張り子のように漆を塗りつけた麻布を土でできた原型に層状に貼っていき、非常に丈夫につくられていることです。内部の土などは一旦抜かれたのち、最終的には内部もしっかり補強するとのこと。このとき、心木以外の材料はほとんど掻き出されるので、全体重量が軽く造ることができます。例えば阿修羅像でも15Kg程度とのこと、だから火事があっても担いで逃げることができたのですね。
玉眼について、玉眼はリアリティを追求していた後に慶派と呼ばれる仏師たちが仏像の目の裏側に水晶などを嵌め込んであみだしたもので、日本独自の手法とのことでした。レプリカで現物の作りをみせていただくことが出来、貴重な体験となりました。講演後も多くの受講者が、レプリカを手に取って見たり、玉眼などについて質問をしていました。

制作当時の色に再現されたレプリカ
今回の講座は2週連続の講座の第1回目、「観たくなる奈良の仏像」と題してご講演頂きました。奈良県の仏像の他、私たちに馴染みのある仏像を中心に、制作過程と、修復について教えて頂きました、次週は、第2回 9月11日(水曜日)「仏像の模造とレプリカ」と題して、模造とレプリカの役割について実際の事例より説明して頂けます。楽しみですね。
さて、文化の秋が近づいてきました、仏像との出会いをもとめて、奈良にお出かけしてみるのは如何でしょうか?