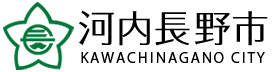本文
農業を始めたい方へ(市外、府外の方も大歓迎!)
農業を始めたいと考えておられる方に対し、就農までの道すじ、サポート体制について、ご案内します。
農家でない方が農業を職業として行うに当たっては、資金や農地の確保など様々なハードルがあります。これらを着実にひとつひとつ解決するために、国・府・市それぞれが新規に就農を希望する方に対して様々なサポートを行っています。
本市においては、就農相談をはじめ、農業研修講座の実施、栽培指導における専門職員の配属や、新規就農者の農業機械購入費用の補助などの支援を行っています。
また、農地を探される方へ農地情報を提供することや、市外の方で河内長野で農業に従事することに関心を持つ方に空き家情報を提供しています。
就農に興味のある方は、自然資本活用課までお気軽にご連絡ください。
~就農までの道すじ・サポート体制~
1.就農の準備を行う
・農業を始めるための情報を集めるには
・農業に関する研修を受けるには
・農業の勉強をするうえで必要な費用を確保するには
・河内長野市に住むには
2.就農を開始する
独立して農業を始める場合
・農地を探す(取得・貸し借り)
・各種の支援制度を利用するには
・作物を販売するには
・作物栽培で疑問があるときは
複数の農業者と共同で農業を始める場合
・農業法人等へ就職するには
3.農業経営を発展させる
・農地の規模を拡大するには
・農機具等の購入資金を調達するには
・生産コストの低減や農作業を効率化するには
・経営管理能力の向上や経営の多角化を目指すには
1.就農の準備を行う
・農業を始めるための情報を集めるには
・農業に関する研修を受けるには
・農業の勉強をするうえで必要な費用を確保するには
・河内長野市に住むには
農業を始めるための情報を集めるには
- 「全国新規就農相談センター」<外部リンク>のホームページを利用する。
- 大阪都市農業情報ポータルサイト(JAグループ大阪)<外部リンク>のホームページを利用する。
- 大阪府農と緑の総合事務所農の普及課<外部リンク>へ就農相談に行く。
- 大阪農業つなぐセンター<外部リンク>(咲州庁舎内)に相談に行く。
- 河内長野市役所自然資本活用課(市役所5階)に相談に行く。
農業に関する研修を受けるには
農地を借りるためには原則として農業経験が必要となります。経験のない方が農業を始めようとする場合、次のような研修を修了することで農業経験として認められる場合があります。受講を希望する研修が農業経験とみなされるかどうかについては、事前に自然資本活用課までご確認ください。(数日程度の短期研修では経験とみなされません。)
- 都道府県の農業大学校や民間の農業者研修教育施設等で研修を受ける。
大阪府農業大学校<外部リンク>
- 河内長野市農業研修講座を受講する。
河内長野市内で就農したい方向けの講座です。例年5月~6月中旬にかけて募集し、7月中旬~12月上旬の期間で講義・実習を行います。
農業の勉強をするうえで必要な費用を確保するには
「就農準備資金」を活用する。
この資金は、就農に向けて必要な技術等を習得する研修期間中の就農予定時に49歳以下の研修生に、最長2年間、年間 150万円を給付するものです。
- 全国新規就農相談センター<外部リンク>
- 大阪府/就農相談窓口について<外部リンク>
- 南河内農と緑の総合事務所<外部リンク>
- 大阪府農業大学校<外部リンク>
- 就農準備資金のページ(農水省ウェブサイト)<外部リンク>
河内長野市に住むには
農業を続けていくためには、就農地の近くで住居を探すことをおすすめします。
河内長野市移住定住相談デスク
本市への移住や定住(住宅を購入して住み続けること)を検討、希望される方をサポートするため、お問い合わせやご相談をお受けしております。詳しくは、移住定住相談デスク(シティプロモーション課)までお問い合わせください。
空き家バンク制度
市内へ定住等を目的として空き家等の利用を希望する方などに対して、その情報を紹介する制度です。詳しくは、まちづくり推進課までお問い合わせください。
市営住宅などの公営住宅や公的賃貸住宅
市営住宅のご案内
府営住宅の募集、入居などのお知らせ(大阪府Webサイト)<外部リンク>
UR賃貸住宅の空室情報(UR都市機構Webサイト)<外部リンク>
2.就農を開始する
独立して農業を始める場合
・農地を探す(取得・貸し借り)
・各種の支援制度を利用するには
・作物を販売するには
・作物栽培で疑問があるときは
複数の農業者と共同で農業を始める場合
・農業法人等へ就職するには
独立して農業を始める場合
農地を探す(取得・貸し借り)
農地は、一般の土地と異なり、原則として農家でなければ売買や貸し借りができません。また、売り農地の情報も一般的にはあまり出てくることはありませんので、農地の取得や利用に当たっては下記の制度の活用をご検討ください。(いずれも農地の貸し借りを行うものです。)
- 河内長野市の「農用地利用集積等促進計画」で利用権を設定する。(お問い合わせは河内長野市農業委員会事務局まで)
各種の支援制度を利用するには
「認定新規就農者<外部リンク>」としての認定を受ける。
一定の要件を満たし、新規就農を計画する青年などに対して、その就農計画を認定する制度です。認定を受けることにより、下記の 「経営開始資金(農業次世代人材投資資金)」や「青年等就農資金(新規就農者向けの無利子資金制度)」等、各種の制度を利用することができます。
所得を確保するには
「経営開始資金<外部リンク>」を活用する。
この資金は、49歳以下の認定新規就農者に、経営開始から最長3年間、1年につき150万円を交付し、就農直後の経営が不安定な時期の所得安定に役立てることを目的としています。
初期投資に必要な資金を確保するには
「経営発展支援事業<外部リンク>」を活用する。
新規就農者に対する経営発展のための機械・施設等の導入を支援します。
農業経営を開始するために必要な資金を確保するには
「青年等就農資金(新規就農者向けの無利子資金制度)<外部リンク>」を活用する。
農業機械を購入するためには
「河内長野市新規就農者支援事業補助金」を活用する。
新規就農者(認定新規就農者としての認定は不要)が耕運機や草刈機等の農業機械を購入する際、1回限り購入費用の2分の1以内(上限10万円)を補助します。購入前に申請が必要です。
農業機械をレンタルするためには
JA大阪南の農業機械レンタルを利用する。
詳しくは、JA大阪南高向営農経済センター(0721-53-0002)まで。
ビニールハウスを設置したいときは
「農業用ビニールハウス設置事業補助金」を活用する。
一定の基準を満たすビニールハウスを設置する際、資材購入費(設置作業費・送料等は対象外)の2分の1以内(上限20万円)を補助します。購入前に申請が必要です。
作物を販売するには
市内の直売所などに出荷
収穫量が少なくても出荷が可能であり、希望価格で販売でき、売れ行きを見て消費者からの評価が分かります。出荷には直売所への出荷者登録が必要となりますが、各直売所により要件が異なりますので、詳細は各店舗にお問い合わせください。
学校給食へ納入
学校給食センターに物資納入業者として登録する。
詳しくは、河内長野市立学校給食センターまで。
なお、「アグリかわちながの」が物資納入業者として登録されておられますので、「アグリかわちながの」に出荷登録し、給食センターへ納入することも可能です。
ふるさと納税の謝礼品として提供
ふるさと納税制度による河内長野市への更なる寄附の促進や、地場産品等のPR・販売促進につなげるため、寄附に魅力ある謝礼品を提供いただける事業者を募集しています。詳しくは、ふるさと納税課までお問い合わせください。
インターネットで販売
ネット販売は、営業時間や場所に制限されることなく販売することができます。
伝票を発行してもらえるなど生産者の手間が比較的少ない産直サイトを利用する方法もあり
ます。
作物栽培で疑問があるときは
市役所自然資本活用課に相談する。
市では販売農家の育成や、農産物出荷の拡大、各地区における地域農業の活性化を目指して、栽培指導における専門職員を配属しています。作物栽培における技術的指導や相談、病害虫、農薬等についての質問などございましたら、お気軽にご相談ください。
複数の農業者と共同で農業を始める場合
農業法人等へ就職するには
「全国新規就農相談センター」のホームページ、ハローワークプラザ難波の農林漁業就職支援コーナー等で、農業法人の求人情報を収集する。
- 農地中間管理機構(一般財団法人大阪府みどり公社)<外部リンク>
- 就農準備資金・経営開始資金<外部リンク>のページ(農水省ウェブサイト)<外部リンク>
- 全国新規就農相談センター<外部リンク>
- ハローワークプラザ難波 農林漁業就職支援コーナー<外部リンク>
3.農業経営を発展させる
・農地の規模を拡大するには
・農機具等の購入資金を調達するには
・生産コストの低減や農作業を効率化するには
・経営管理能力の向上や経営の多角化を目指すには
農地の規模を拡大するには
- 上記の利用集積制度または農地中間管理機構を活用する。
- 農地の紹介を受けやすくするため、「認定農業者」の認定を受ける。
農機具等の購入資金を調達するには
「認定農業者」の認定を受けると、スーパーL資金等の低利融資を受けることができるほか、一部補助金の受給対象となる事ができる。
生産コストの低減や農作業を効率化するには
集落営農組織を結成し、農機具の共有化や役割分担を行い、共同で農業を行う。営農組織に対しては、一部補助金の受給対象となる事ができる。
経営管理能力の向上や経営の多角化を目指すには
- 法人格を取得し、農業法人を立ち上げることで、家計と経営の分離を図り経営を明確にする。
- 6次産業化の方策を検討する。6次産業化に取り組む農家に対しては、一部補助金の受給対象となる事ができる。
6次産業化とは、農家が農産物の生産(1次産業)だけでなく、加工(2次産業)、流通・販売(3次産業)にも取り組むことで、生産物の価値を向上させようというものです。
食品加工のための機械購入やチラシの作成経費など、生産した農産物を加工し、販売するために必要な経費の1/2(上限30万円)を補助します(6次産業化促進事業補助金)。
- 認定農業者制度について(農水省ウェブサイト)<外部リンク>
- 大阪版認定農業者制度について(大阪府ウェブサイト)<外部リンク>