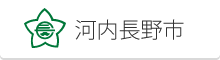本文
河内長野版歳時記プロジェクト 市内の祭礼・伝統行事等の映像について

「河内長野版歳時記プロジェクト」の一環として、市内の市指定無形民俗文化財等を紹介する映像を制作しました。
ぜひご覧ください。
加賀田神社のオコナイ
加賀田地区に伝わる行事、オコナイ。
およそ350年にわたって伝わる行事で、毎年1月3日に行われます。
「修正会(しゅしょうえ)」ともよばれる行事です。
唯一無二のしきたりを通じて、豊かな実りと地域の安寧を祈ります。
※非公開
八幡神社の勧請縄かけ
流谷地区の八幡神社で行われる、勧請縄かけ。
毎年1月6日ごろに、神社の前を流れている流谷川に勧請縄をかけます。
石清水八幡宮からご神体を勧請した日にちなんで、この日に行われるようになったと伝わります。
ムラの境に勧請縄をかけて疫病や魑魅魍魎(ちみもうりょう)が入ってこないようにして、無病息災と五穀豊穣を祈願する意味があるとされています。
天野山金剛寺正御影供百味飲食
天野山金剛寺の正御影供百味飲食(しょうみえくひゃくみのおんじき)は、平安時代後期から続くとされる正御影供(毎年4月21日の弘法大師の命日に修される法要)の中で行われる民俗行事です。
百味飲食といわれる、里の幸・山の幸・海の幸からなる多くの供物が作られ、祭当日に弘法大師の御影の前に供えられます。
西代神楽
毎年10月、西代神社の境内で行われます。
伊勢神楽の影響を受けた獅子舞で、鈴の舞、銜之剣(くわえつるぎ)、四方掛(しほうがかり)、歌剣、吉野舞、扇の舞、玉の舞、神来舞(しぐるま)、白獅子、花の舞の10曲が伝わっています。
享保17年(1732)、西代藩主であった本多忠統(ただむね)が神戸(かんべ)藩に転封された際、その徳をしのんで西代神社に奉納したのが始まりとされます。
日野地区獅子舞
毎年10月、日野と高向で披露されます。
日野地区に数百年の昔から伝えられている獅子舞で、「六斎念仏」「人形芝居」などと深いつながりをもっているといわれ、巣垣の舞、乱曲の舞、床几(しょうぎ)の舞、花の舞、地巣籠の舞、風の舞の6曲が伝えられています。
毎年10月の春日宵宮ではみのでホールで、翌日に高向神社で奉納されています。
八幡神社の提灯祭り
八幡神社の祭礼、提灯祭り。
毎年10月、八幡神社の境内で、流谷・下天見地区の人々が提灯を持って集まります。
人々を固く結び続ける伝統行事が、山間の秋を一層深めていきます。
蟹井神社の提灯祭り
蟹井神社の祭礼、提灯祭り。
毎年10月、蟹井神社の境内で、上天見地区の人々が提灯を持って集まります。
それぞれの地区が受け継いできた祇園囃子が、谷あいの里に響きます。
天神社の提灯祭り
天神社の祭礼、提灯祭り。
毎年10月、天神社の境内で、滝畑地区の人々が提灯を持って集まります。
江戸時代、神社から祇園囃子が聞こえ、提灯の明かりが登っていくのが見えたことから、山の上の神社に登り、提灯を奉納するようになったと伝わります。
長野神社のタイマツタテ
長野神社の神事、タイマツタテ。
毎年10月11日、境内に氏子や関係者が集まり、大松明に御神火がともされます。
大松明神事とも呼ばれ、神社の御祭神を迎えるために松明を焚いたことがはじまりとされています。
住吉神社の馬かけ
住吉神社の祭礼、馬かけ。
毎年10月、住吉神社の境内で、小山田地区の人々が馬とともに集まります。
はるか昔、神功皇后が凱旋の折、裸馬の競走を奉納したことに由来する祭礼とされます。
下里の亥の子
下里地区の伝統行事、亥の子。
毎年11月、子どもたちが地区を回り、各家の玄関で亥の子唄を歌いながらイノコツキと呼ばれる棒状の藁で地面を叩きます。
この1年の収穫を祝うとともに、来年の豊作を祈る行事と考えられています。