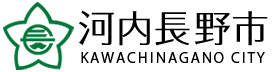本文
【受付終了】調整給付金(定額減税補足給付金)
調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる個人への給付金)
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において『定額減税』が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられない(定額減税の額が、定額減税前の税額を上回る)と見込まれる人に対しては、その差額を調整給付金として支給します。
※この給付金を受けるための申請受付は、令和6年8月30日(金曜日)で終了しました。
- 対象となる人には、令和6年7月頃、個別にお知らせを送付する予定です。
- 支給を受けるための手続きは、「公金受取口座」の登録の有無により異なります。詳しくは下記の手続き方法などをご確認ください。
(参考)「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)のご案内 [PDFファイル/1.58MB]
定額減税については、こちらをご覧ください。
国税庁_定額減税特設サイト https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm<外部リンク>(外部リンク)
個人住民税の定額減税について(令和6年度個人住民税(市民税・府民税)における定額減税について)
支給対象となる人
次のすべてに該当する人が調整給付金の支給対象となります。
- 河内長野市で令和6年度の住民税(市民税・府民税)が課税されている
- 令和6年分推計所得税額(※)、令和6年度住民税の所得割額について、少なくともどちらかが0円ではない
- 定額減税可能額が、減税前の税額を上回る
※定額減税は令和6年分所得税から行うので、調整給付金の算定も令和6年分所得税をもとに行う必要がありますが、令和6年分所得税は調整給付金の支給時点で確定していないため、令和5年分所得等をもとに推計した額を「令和6年分推計所得税額」として、これをもとに調整給付金の算定を行います。令和6年分所得税が確定後、調整給付金の不足が判明した場合は、令和7年に不足分を給付予定です。
所得税が非課税で、令和6年度住民税の所得割も課税されていない人は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象となりません。
令和6年度新たに世帯全員が住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対しては、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
新たに住民税が「非課税」または「均等割のみ課税」となった世帯への給付金
支給額
調整給付金の額は個人ごとに異なります。
所得税、住民税所得割についてそれぞれ「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。
「控除不足額」の算出は、「定額減税可能額」から「減税前の税額」を差し引いて行います。
「定額減税可能額」の計算方法、「調整給付金」の計算方法は次のとおりです。
- 定額減税可能額の計算
・所得税の定額減税可能額は、本人・扶養親族(配偶者を含む)1人につき3万円です。
・住民税の定額減税可能額は、本人・扶養親族(配偶者を含む)1人につき1万円です。
→例えば本人が配偶者と子1人を扶養している場合、
・所得税の定額減税可能額は、3万円×3人分(本人・配偶者・子)=9万円、
・住民税の定額減税可能額は、1万円×3人分(本人・配偶者・子)=3万円 となります。
- 調整給付金の額の計算
(1)所得税と住民税それぞれの控除不足額を、次の計算式により算出します(※)。
- (所得税の定額減税可能額)-(減税前の令和6年分推計所得税額★)=(所得税の控除不足額)
★令和6年分推計所得税額とは令和5年分所得等をもとに推計した所得税額のことです
- (住民税の定額減税可能額)ー(減税前の令和6年度住民税所得割額)=(住民税の控除不足額)
※算出した結果の額が0円よりも小さい場合は、0円とします。
(2)(1)で計算した、所得税と住民税の控除不足額を合計し、1万円未満の端数を切り上げます。
(所得税の控除不足額)+(住民税の控除不足額)=(調整給付金支給額(1万円未満切上げ))
手続方法など
調整給付金の支給を受けるための手続き
・調整給付金の支給対象となる人には、令和6年7月頃、個別にお知らせ文書をお送りする予定です。
・支給を受けるための手続きについては、「公金受取口座」の登録がある人とない人で異なります。(「公金受取口座」とは、マイナンバーカードに紐づいた、「マイナポータル」等から登録する公金受取口座のことです。)
「公金受取口座」の登録がある人の場合
「公金受取口座」の登録を済ませている人に対しては、「支給のお知らせ」をお送りする予定です。
「支給のお知らせ」を受け取られた人がお知らせの内容どおり支給を受ける場合は、手続き不要です。
(辞退される場合や公金受取口座を変更された場合のみ、届出が必要となります。)
「公金受取口座」の登録がない人の場合
「公金受取口座」の登録がない人に対しては、「支給確認書」をお送りする予定です。
「支給確認書」を受け取られた人が支給を受けるためには、「支給確認書」に必要事項を記入のうえ返送(記入内容によっては添付が必要な書類もあります)するか、もしくは「支給確認書」に記載のQRコードからオンラインで必要事項の登録・送信を済ませてください。(いずれの場合も令和6年8月30日(金曜日)までに返送・送信されたもののみ受付します。期限を過ぎるといかなる理由があっても給付できません。)
給付金にかかる文書の送付先を、住民票の住所地以外に変更する場合
引っ越し、出産・出張等による不在、入院や施設入所、DV避難等で住民票の住所地にて確認書を受け取れない場合には、(送付先変更届 [PDFファイル/750KB])を提出してください。
送付先変更届を提出するときに添付が必要となる書類は次のとおりです。
1.本人が住所地以外で受け取る場合
・本人確認書類
・変更後の送付先の住所が確認できる書類(電気・ガス・水道の領収書のコピーなど)
2.やむを得ない事情等により本人以外の人が代理で受け取る場合
・本人確認書類
・代理人の本人確認書類
3.法定代理人が受け取る場合
・代理権を証明する書類(成年後見登記事項証明のコピー)
■提出期限
令和6年8月30日(金曜日)
(原則、郵送により提出してください。)
■提出先(郵送先)
〒586-8501
大阪府河内長野市原町1-1-1
河内長野市役所 低所得者支援および定額減税補足給付金担当
※お問い合わせは河内長野市専用コールセンター(56-2511)まで
お問い合わせ
河内長野市専用コールセンター
番号:0721-56-2511
時間:午前9時から午後5時30分(土日祝を除く)
定額減税や給付金をかたる不審な電話やメールにご注意ください
個人情報、通帳、キャッシュカード、口座番号、暗証番号などの詐取にご注意ください。
給付金の申請内容に不明な点があった場合などには河内長野市から問い合わせを行うことがありますが、メールで銀行の口座情報を聞き出すことや、ATM(現金自動預振機)の操作をお願いすること、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
国(国税庁や税務署)、市役所等の公的機関の職員をかたり、「定額減税の件」「給付金の件」などの電話やメールにより銀行の口座情報を聞き出そうとする事案や、還付手続きのためとウソを伝えATMを操作させ振込を行わせる事案の発生が確認されていますのでご注意ください。
銀行の口座情報などの入力を求められたときなどは、情報を詐取される恐れがありますので、その発信元が信頼できるものであるかどうか、十分にご注意ください。
心当たりのない電話があった場合は、絶対に口座情報などを伝えないようにしてください。
心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合は、絶対に、メールに記載のURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないでください(心当たりのないメールはすぐに削除してください)。
定額減税詐欺注意リーフレット [PDFファイル/490KB]
【定額減税や給付に関連した特殊詐欺についての注意喚起:国税庁HP<外部リンク>】
https://www.nta.go.jp/information/attention/attention.htm
この給付金の性質について
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」の規定により、この給付金は差押禁止及び非課税の対象となっています。