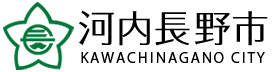職員採用 能登半島地震 モックルMaaS ご遺族サポート窓口が予約制に ふるさと納税 内部統制
本文
市長コラム(令和5年度)
社会潮流の先端都市として(令和5年4月)
日本の昨年の出生者数が、1899年の統計開始以来初めて80万人を下回ったことが話題になっています。河内長野市もその影響を受け、昨年の出生者数は500人を下回りました。本市においては、南花台地区での施設一体型小中一貫教育推進校の整備をはじめ、公立学校の小規模化対応を段階的に行います。
その一方、いわゆる団塊の世代が後期高齢者となることもあり、本市においては、今後5年以内に4人に1人が後期高齢者となる見込みです。それを見据えて、移動支援をはじめとした高齢者の生活支援を拡張します。
本市は、社会潮流の先端市として、子育て支援総合拠点「あいっく」を基軸とした子育て支援、英語村構想事業を中心とした多文化共生社会への対応、最先端技術を利用した自動運転バスや遠隔診療の実証実験など、社会課題の解決に向け、新たな取り組みを積極的に実施してまいります。また、現在はデジタル化への過渡期であるため、デジタルデバイド(情報格差)が生じていますが、その解消にも取り組んでまいります。
高齢者向けの移動支援(令和5年5月)
現在、日本の後期高齢者(75歳以上の人)は約2000万人、本市では約2万人にも上ります。運転に不安を感じるようになった高齢者は、運転免許証の自主返納を考えながらも、自動車がなければ移動が不便なので返納をためらうという状況にあるかもしれません。特に、3世代などの大家族が減少し、核家族化が進んでいる現状では、家族に移動を頼るということも容易ではありません。
バスのような公共交通は、利用者が一定数いることで成り立ちますので、どの地域でも路線定期運行を実施できるわけではありません。そこで、公共交通を補完するものとして、市町村やNPO法人などが主体となる自家用有償旅客運送や地域住民の支え合いによる移動サービスなどが考えられます。また、本市では、電動カートを用いた自動運転バスなどの本格的実施に向け、実証実験中の取り組みもあります。
後期高齢者の数は今後増加傾向にありますので、既存の公共交通とのすみ分けや連携のあり方などの協議を進めながら、各地域の実情に合った移動手段が確保できるように、市として取り組みを支援してまいります。
産業誘致で地元雇用創出を(令和5年6月)
本市は、昭和29年に人口約3万人で始まり、同44年には5万人を、同63年には10万人を超えましたが、人口減少という社会潮流の中、出生数の増加や子育て世代の転入など動きはあるものの、自然減の影響もあり、この4月に10万人を割りました。大阪都市圏のベッドタウンという位置づけで発展してきた本市ですが、市の活性化のためにも、産業誘致で地元雇用を創出することが喫緊の課題となってきました。
本市においては、産業用地に適した平坦な場所が限られているのが現状ですが、高向・上原地区および小山田西地区では、産業用地の確保に向け土地区画整理事業を進めています。加えて、多くの市内事業者からのご要望もあり、工業団地に隣接する赤峰グラウンドの産業用地化も検討しています。
グラウンドのスポーツ利用者には、活動に切れ目が生じないよう、代わりの施設をご提案させていただき、さらに将来的には、小山田地域などの新たな場においてスポーツ施設の集約・充実を図ります。また、憩いの場として利用されている市民に対しては、産業用地内に憩いの場を設け、さらに寺ケ池公園の機能充実と魅力向上も図ってまいります。
インターネット上にも基本的人権を(令和5年7月)
SNSやインターネット上の情報は、自分の興味や関心のある投稿をフォローしたり、拡散したりすることで、同じような意見ばかりが流れてくる仕組みになっています。「いいね」や拡散などにより、誰かに認められていることが可視化されると自身の承認欲求がより一層駆り立てられます。
これは見方を変えると、SNSを利用する際の態度・意見が同じ人ばかりの閉じられた空間を形成し、特定のタイプの情報のみが正しいという錯覚を引き起こしかねません。気づけば自分が誰かを傷つけているかもしれません。
しかし、個人が持てる知識をもって「何が正しい情報か」判断するのには限界があります。つまり、インターネット上にも自分の権利と相手の尊厳を守る基本的人権が必要不可欠になってきます。
河内長野市では、「差別は許さない」との認識のもと、今後も「思いやりとぬくもりのある、一人ひとりが尊重しあえる共生のまち」の実現に向けて、施策を進めていきます。
一人ひとりが自分事として捉え、相手の立場になって考え、行動することを心がけていきましょう。
インクルーシブ社会の構築に向けて(令和5年8月)
最近、「インクルーシブ」という用語を耳にする機会が多いと思います。直訳すると「包括的」という意味で、多様性を尊重し、主に障がいのある人と障がいのない人が共生していくことを目標としています。
令和3年に河内長野市手話言語条例が制定されました。条例の前文にも記載されている通り、「手話は、音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使って表す言語である」という理念が背景にあります。成人のつどいなど、本市の大きな催しには手話通訳を配置するようにしています。インクルーシブ社会の構築に向けた一歩です。
障がいには、身体、知的、精神( 発達含む) があり、本市において、いずれかの障がい者手帳をお持ちの方が約6200人おられます。私の亡母も、股関節が脱臼した状態で生まれたらしく、私が中学生になったころから歩行が困難になり始め、障がい者手帳を持ち歩いていました。
市民のみなさんが、障がいの有無に関係なく、相互に人格および個性を尊重し合いながら共生することができる地域社会の構築を目指してまいります。
地域のお祭り(令和5年9月)
コロナ禍が少し落ち着き、4年ぶりに多くの夏祭りが開催されました。主催は、自治会、青年団、青少年健全育成会、神社など、地域によって異なりますが、地域のみなさんのために多くの関係団体がご尽力いただきました。夏祭りの中でも、三味線や太鼓、エレキギターなどに合わせて歌い手さんが「河内音頭」を歌い、櫓の周りで踊る「盆踊り」が人気のようで、子どもたちにとっても、郷土における良き思い出となったことでしょう。
また、秋祭りに関して、河内長野市では、地車、神楽、獅子舞、提灯行列などが催されます。中には、本市の無形民俗文化財に指定されている祭りもあります。人気で言えば、地車の豪快な「ぶん回し」。市外からも多くの見物客が来られます。本市における地車の歴史は古く、1863年に高向神社に奉納された絵馬には、上高向、中高向、下高向の3つの地車が描かれており、本市の地車に150年以上の伝統があることが分かります。
コロナ禍で外出が抑制されたり、行事が中止になったりしましたが、今年の夏祭りや秋祭りを通じて、地域の絆がより一層深まることを願っています。
特殊詐欺にご注意!(令和5年10月)
本市が誇れることの一つに、「安全・安心なまち」が挙げられます。ここ5年間における犯罪発生率が、大阪府内33市で最小です。刑法犯認知件数を人口で割ると犯罪発生率が算出されるのですが、毎年最小1位か2位で、ここ5年間で計算すると最小1位です。これは、河内長野警察や河内長野防犯協議会をはじめ、地域のみなさんの地道な活動の結果です。
本市の場合、一番深刻なのは特殊詐欺です。高齢者から、老後生活のために蓄えてきた大切なお金をだまし取ろうとする悪質な犯罪です。特殊詐欺には、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、還付金等詐欺などがあり、市では自動通話録音装置の無料貸出や、防災行政無線による注意喚起を行っています。また、河内長野警察の依頼により、私の声で録音した還付金詐欺の注意喚起メッセージを、無人ATMコーナーで流しています。
自分だけはだまされないと思っている方が多いと思いますが、詐欺グループは言葉巧みにあの手この手でお金を奪い取ろうとします。今一度、特殊詐欺にはご注意を!そして、地域のみなさんも、だまされているかもしれないと思う高齢者を見かけたら、思い切ってお声がけを!
文化祭の意義(令和5年11月)
11月3日の「文化の日」に合わせて、河内長野市では毎年、その前後に文化祭が開催されます。書展、華展、茶会のような日本古来の伝統文化だけでなく、ワールドダンスやフラワーデザイン展のような新しい文化を披露される方々もおられます。どの催しも普段の練習や活動の成果を発揮する場ですので、一見の価値があり、河内長野の秋を華やかに彩ります。
文化祭には、市民の絆を深める効果もあります。参加者同士が、文化祭に向けて切磋琢磨したり、一緒に作品を作り上げたり、共通の趣味・興味を持つ者同士が密になる機会ですし、また、文化祭を見に来る人たちとも、コミュニケーションを取ったり参加していただいたりすることによって、文化の輪が広がっていきます。
文化は、豊かな人間性を育む機会を与えてくれますので、本市の発展には不可欠で、次世代に継いでいくものです。コロナ禍で人と人とのつながりが希薄になりがちでしたが、文化祭を通して、市民のみなさんの絆が深まるとともに、心が豊かになることを願っております。
河内長野市の行政改革(令和5年12月)
総務省の調査データを基に、時事通信社の関連団体「時事総合研究所」が作成した日本全国1741市区町村の「行政サービス改革度ランキング」で、河内長野市が2023年度の第1位となりました。本市職員の普段の努力が結果として表れました。このランキングは今年度から始まったところですが、同じ手法を使って昨年度のデータを点数化すると、本市が2022年度も第1位ということです。
地方自治体は、行政として効率性ばかりを追求できないのですが、少子高齢化・人口減少という社会潮流で財政難が続く中、ある一定の効率性を考えていかなければなりません。本市では、現行の業務を見直してスリム化することから始め、市役所内すべての業務を見直しました。そのステップを経て、ある程度標準化できる業務については、外部委託やAIを活用し進めています。また、施策の円滑な推進のため、組織機構の見直しも実施しています。
行政として時代の変化に対応していく必要がありますので、本市は市民サービス等の向上に向け、行政改革を継続してまいります。
ライトアップによる啓発活動(令和6年1月)
市では、関係団体と一緒に様々な啓発活動を実施しています。窓口に啓発ポスターを掲示したり、ラックに啓発チラシを配架したり、駅前で啓発グッズを配布したりするなど、目的に合わせて様々な方法で啓発活動を行っています。
また、新しい試みとして、昨年7月から、キックスの屋上で日暮れから午後10時までライトアップを実施し、併せて1階のエントランスホールで啓発内容を展示するという手法が加わりました。例えば、7月は「社会を明るくする運動」の強調月間で、そのシンボルカラーである黄色にライトアップしました。ほかにも、10月の「乳がん啓発ピンクリボン」月間にはピンク色にライトアップしました。昨年は、合計8種類の啓発活動をライトアップとあわせて実施しました。
キックス屋上のライトアップ機能は元から備わっており、LED化された照明にシンボルカラーとなる色のフィルムを被せることによって、工夫して色を出しています。写真映えしますので、若い方々を中心にSNS投稿などで、啓発活動がより一層効果を発揮することを期待しています。
消防・救急行政の広域化(令和6年2月)
日本全国で人口減少・少子高齢化が進み、事務作業の効率性が求められる中、隣接する市町村で連携して取り組む広域行政が増えています。河内長野市の場合、まちづくりや福祉に関する事務の一部を共同処理するため、富田林市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村の3市2町1村で、南河内広域事務室を設けています。また、ごみ処理に関しては、3市2町1村で一部事務組合を設置しています。
今年4月からは、消防団事務を除く消防事務を共同処理するため、大阪狭山市を除く2市2町1村に、柏原市、羽曳野市、藤井寺市を加えた5市2町1村で大阪南消防組合を立ち上げることになりました。消防の広域化の検討を始めてから5年以上が経過しましたが、その間、財政面や体制などの46項目について様々な観点から議論を重ね、広域化の実現に至りました。
消防・救急行政の広域化により、住民サービスの向上、人員配備の効率化、車両や資機材の共有による消防・救急体制の強化などが図られます。市民生活の安全・安心の確保だけでなく、持続可能な消防・救急体制が期待されます。
有効期限にご注意ください!(令和6年3月)
市では、国の臨時交付金などを活用し、市民向けに様々な取り組みを実施してきましたが、年度末にあたる3月に有効期限を迎える事業がいくつかあります。たとえば、75歳以上の高齢者に「おでかけチケット」(バス無料券とタクシー200円券各5枚分)をお送りしましたが、有効期限は3月31日です。また、河内長野市内のバスが乗り放題になるモバイル専用「モックルチケット」(ホリデーとオフピークの2種類)をキャンペーン価格200円で購入できますが、購入期限は3月25日午前10時で、有効期限は3月31日です。市内の店舗や施設で使える特典クーポンも付いています。公共交通利用促進のためにも積極的にご利用ください。
また、地域通貨「モックルコイン」を、昨年8月から全市民に2000円分、加えて1月から20歳以下の全市民に1万円分をお送りしました。どちらも有効期限は3月15日です。本市における地域経済活性化のためにもぜひご利用ください。
いずれの事業も、期限を過ぎますとご利用できませんので、有効期限に注意してご活用ください。