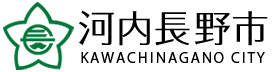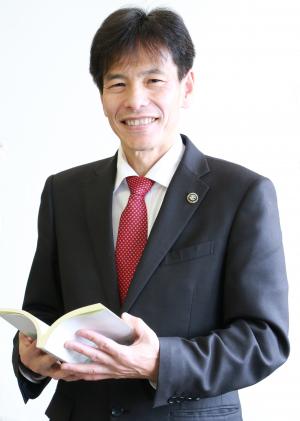職員採用 能登半島地震 モックルMaaS ご遺族サポート窓口が予約制に ふるさと納税 内部統制
本文
市長コラム(平成31年度)
このページでは、私の想いを市民のみなさんと共有できればと考え、定期的に発信してまいります。
図書館の有効利用を(平成31年4月)
みなさんは、一年に何冊ぐらいの本を読まれるでしょうか。私は、本屋さんで話題の本を衝動買いし、そのまま本棚にしまっておくことが多いタイプです。小学生のころは豊臣秀吉や野口英世など伝記をよく読みましたし、西代神社横にあった旧市立図書館にも自転車で通いましたが、正直なところ、現在はあまり本を読みません。読書離れは社会問題にもなっていますが、表現力豊かな人は決まって読書家で、うらやましく思うことが多々あります。
さて、みなさんは市立図書館を利用されているでしょうか。50万冊近くの蔵書があり、それらはインターネットを通して検索でき、予約も可能です。
その他、図書館では様々なサービスを提供しており、調べたい内容を図書館司書に相談すれば、調査の手伝いをしてくれます。例えば、私の場合、「楠公駅伝」について調べたことがあるのですが、インターネット検索では思うような情報が得られず途方に暮れていたところ、図書館から郷土資料を含めたいくつかの文献を紹介され、有用な情報を得ることができたという経験があります。
今後は、新たに英語多読本コーナーを整備し、国際交流協会と連携して英語のおはなし会も開催する計画です。ぜひ、市立図書館をご利用ください。
経営戦略をいかした組織改革(令和元年5月)
私は市長就任前に、神戸大学大学院で社会人や留学生を相手に「経営戦略論」を教えていました。経営学の中で、「組織は戦略に従う」という基本的な考え方があり、戦略をうまく機能させるために、組織構造が重要であると考えられています。
一方、「戦略は組織に従う」という逆の見方もあり、組織の特徴を生かして、戦略を立案することが重要という見解です。どちらも、ある意味正しく、組織と戦略は相互に依存する関係だということを示唆しています。
市役所においては、時の流れに合わせるべく、あるいは、施策を効果的に実現させるべく、組織機構の見直しを行い、併せて人事異動を行います。例えば、昨年度は、空家または空地が急激に増加してきたことにともない、空家対策係を新設し、今年は保健福祉の支援を充実させるために、保健福祉部を、市民保健部と福祉部に分割しました。
人事配置に関して、適材適所を第一に考えますが、新しい経験を積ませるために、ジョブ・ローテーションも行います。市役所には様々な人材がいますが、すべての職員が資源となり、河内長野市の行政を担っています。これからもスマートシティを有効に推進するために、組織を構築していきます。
英語力を高めるために(令和元年6月)
私が今までの人生で最も苦労したことの一つは英語力の習得でした。私が大学院生のころは、インターネットも電子辞書もなく、 いつも厚さ5センチ程度の英和辞典・和英辞典の2冊を鞄に入れ、事あるたびに辞書を引いていました。その甲斐あって、30歳になる前に英検一級に合格しました。
しかしながら、外国人と議論するにはまだ英語力が足りず、 30代では様々な工夫と努力で英語力に磨きをかけ、40歳になる前には、留学生を相手に講義型だけでなく、議論型の英語授業も行えるようになりました。ただし、今でもハリウッド映画は半分ぐらいしか聞き取れません。
さて、これからは、世界を相手にするグローバルの時代です。英語が話せれば、20億人近くの人々と話せます。語学を習得するには、 若ければ若いほど効果があります。日本では普段の生活で英語を使うことはまれですので、子どもたちに英語に興味を持ってもらう機会を作る必要があります。そこで英語村です。
韓国や台湾では、様々な形態で英語村が作られました。日本でも、東京都英語村をはじめ、大阪英語村や近畿大学英語村などが存在し、本市も小規模ながら、グローバルな人材育成に向け、英語村事業を始めます。みなさんご期待ください。
日本遺産認定を契機に(令和元年7月)
先月、本市が誇る中世文化遺産を活かしたストーリーが日本遺産に認定されました。この認定を契機に、観光地としても発展すべく、「3つの取り組み」を計画しています。
まずは「広域連携」。本市は、高野街道で世界遺産の高野山と、世界遺産登録への勧告を受けている百舌鳥・古市古墳群の間に挟まれています。両地域と連携することで、訪日外国人観光客などの滞在型観光振興を推進していきます。
次に「楠公さん大河ドラマ誘致活動とのタイアップ」です。歴史文化遺産という有形・無形の「モノ」だけでなく、中世のサムライヒーロー楠木正成公という「ヒト」も活かし、楠公ゆかりの地巡りにつなげていきます。
最後に「郷土愛の育み」。市外に向けて発信するだけでなく、市民のみなさんの郷土愛を深めることで、定住人口の維持をめざします。長く住んでいると、地域の良さを見失いがちですが、都心に近く自然と歴史に囲まれた、こんな素敵なまちは他にありません。地元の歴史文化遺産を訪ね回り、魅力を再発見することも観光です。
日本遺産という冠をどういかしていくか、市として、これからが肝心です。
食事と健康管理(令和元年8月)
健康管理という点で、普段の運動に加え、日常生活における食事の位置づけが重要視されていますが、私は食育を十分に受けなかったせいか、偏食、孤食、不規則な食事と、反面教師のような存在です。
ほとんどの市民の方々は、一日三食を通じて、栄養バランスの取れた食事を摂り、食の味覚や食事中の会話を楽しむことが大事だと認識していると思います。しかしながら、とくに働いている方は、多忙な生活の中で、おにぎり、菓子パン、弁当などを一人でさっと食べ、他の事に時間を使うことが多いのが現状だと思います。さらに言えば、朝食を抜いたり、仕事場から帰宅して寝る前に夕食を食べたり、パソコンやスマートフォンをいじりながら食べるなど、健康管理という点では好ましくありません。
医食同源という言葉があります。自戒の念を込めて、いつまでも健康でいたいのであれば、食事について真剣に考えるところから始めてみてはいかがでしょうか。私も朝食からしっかりと食べることを意識していきたいと思います。
受け継がれる平和への想い(令和元年9月)
子どものころ、両親からよく戦時中の苦労話を聞かされました。そのたびに、平和な時代に生まれて良かったなぁと子ども心に思ったものです。
一昔前、8月15日の終戦記念日が近づいてくると、テレビではアニメ映画「火垂るの墓」が定番のように放送されていました。悲しい結末がわかっているのに、何度も観て涙してしまいました。
今、若者の間では、アニメの舞台となった場所を訪れる「聖地巡礼」が流行していますが、この映画に縁のある石屋川や御影小学校などを見て回ったことが、私の人生で唯一の聖地巡礼です。
今年は、「この世界の片隅に」を観る機会がありましたが、どちらの映画も「戦争の悲惨さと命の尊さ」をとても丁寧に伝えていると感じました。
戦後74年が経ち、戦争の記憶の風化が懸念されていますが、本市では、人権協会による「愛・いのち・平和展」や、小・中学校での平和教育などを通じて、平和の大切さが受け継がれています。
改めて、戦争で犠牲となられた方々を追悼するとともに、世界の恒久平和を祈念します。
公共交通のすすめ(令和元年10月)
人口が増加していた時は、全国的に電車やバスの新しい路線ができ、本数も増えました。ところが、人口減少時代に突入した今、利用者が少ない路線は、経営上の理由で、本数が減らされたり、状況によっては、廃止されたりしています。
今後、公共交通を維持していくには、利用者を減らさないよう、住民の皆さんができるだけ自動車の利用を控えて、もっと公共交通を利用することが大切です。
運転免許証を返納した高齢者やまだ取得できない子どもたちは、生活する上で公共交通に頼らなければならず、特に路線バスの利用者を減らさないよう、地域ぐるみで利用促進に取り組むことが必要です。
私は、移動中に仕事や休憩などができるので、自動車を運転するよりも電車やバスをよく使います。また、公共交通を使うと駅やバス停まで歩いたり、乗り換えで階段を昇り降りしたりするなど、自然と運動量も増え、健康増進に役立ちます。
「公共交通よりも自動車のほうが便利」という意見が多いとは思いますが、皆さんも、時々、公共交通を利用されてはいかがでしょうか。
大阪南部高速道路の必要性(令和元年11月)
みなさんがどこかへ遠出する時、高速道路に乗るまでが大変だと感じたことはありませんか。
府内33市(9町1村を除く)の中で、高速道路のIC(インターチェンジ)がないのは本市を含めて4市だけで、さらに市の中心部から最寄りのICまで最も遠いのが本市です。高速道路への距離だけが、本市の少子高齢化の要因とはいえませんが、全国的に交通の利便性や移動時間の短縮を求める風潮が高まっているのは事実です。
雇用創出、そしてまちの活性化のために、新たな企業を誘致すべきというご意見をよく伺います。しかし、物流環境が不利なままでは、企業誘致や産業振興は容易ではありません。本市商工会も地域の事業継続のために、大阪南部高速道路(略して「大南高」)の実現を熱望されています。
また、大規模災害発生時の迅速な対応、救助隊の移動や救援物資の運搬などからも実現は極めて重要だと感じています。
11月からは、早期事業化を求める署名活動を始めます。今後も大南高事業化促進協議会の会長として、国や関係機関に要望を行っていきますのでご期待ください。
楠公さん大河ドラマ誘致の現状(令和元年12月)
「楠木正成・正行親子をNHK大河ドラマに!」という目標の下、署名などの誘致活動を展開しています。地方自治体からなる「楠公さん大河ドラマ誘致協議会」と、寺社や民間団体などからなど「楠公ツーリズム推進協議会」が連携しながら機運を高めています。前者は私が会長を務め、現在55市区町村が加入、後者は、永島全教・観心寺住職が会長を務め、現在33団体が加入しています。
特筆すべきは、全国の数ある大河ドラマ誘致協議会の中で、最大規模を誇り、府内では約8割の市町村が加入し、さらに関西のすべての政令指定都市(大阪市、堺市、京都市、神戸市)が加入していることです。
現在、大阪・関西万博が開催される2025年までの実現をめざし、NHK大阪放送局や東京本部に何度も要望に伺っています。1991年に「太平記」が大河ドラマになったのですが、主に北朝の足利尊氏側から見たドラマとなっていましたので、今度は同じ時代を南朝側から見たドラマで描いてほしいという願いも伝えています。
本市の活性化のために、署名活動や機運醸成へのご協力をお願いします。
アスマイルで明日を笑顔に(令和2年1月)
一年の計は元旦にありということわざがあります。みなさん、それぞれ計画を立てて日々努力されると思いますが、その一つに健康づくりを加えてはいかがでしょうか。
例えば、毎日5,000歩を歩くことや30分間走ること、栄養バランスの取れた食事を摂ることなど。ただし、計画を立てる以上に、有言実行していくことが肝心です。
そこで、12月にはテレビCMも流れていた府が提供するスマートフォン無料アプリ「アスマイル」の活用をお勧めします。
歩数計機能を使えば、毎日の歩数がアプリに自動的に記録されます。また、体重や血圧などの入力や様々な健康づくりがポイントとなり、一定数に達すると毎週・毎月の抽選に参加できます。
私の場合は一日平均で約7,000歩。現在、市内で登録している約700人のうち181位です。周りには3,000円分の電子マネーが当選した人もいますが、私はまだ20回以上はずれが続いています。
今後は、市民のみなさんが毎日を健幸(健やかで幸せ)に過ごせるよう、府とも協議し、アスマイルに本市独自の上乗せポイントを検討します。
まずは健康第一です!
成人を迎えるにあたって(令和2年2月)
今年、河内長野市で新成人となる方は1,064人です。成人になるということは、「一人前」になることで、大人として様々な権利を得ると同時に、様々な社会的責任を負うことになります。ただ、環境が大きく変わるわけでもないので、成人を自覚することはあまりないでしょうが、成人式を契機に大人への仲間入りを意識してください。
今日まで、愛情を注いで育てて下さったご両親をはじめ、教育活動や生活指導に携わって下さった学校の先生、登下校時の見守り活動をして下さった地域の方々などに改めて感謝して頂きたいと思います。また、これからどういう職業に就いてどう生きていくのかを、自立心を持って真剣に考えてください。
市長という立場からすると、このまま当市に残って当市発展のために貢献してほしいという気持ちがあります。その反面、若者には、世界中で活躍してほしいという思いもあります。
どこに住むことになろうと河内長野で育ったことを誇りに思って下さい。故郷河内長野は、皆さんをいつでも温かく迎えます。ご成人おめでとうございます。
SDGs達成に向けて(令和2年3月)
最近、17色からなる車輪のようなバッジを身に付けた方々を見かけませんか。それはSDGs(持続可能な開発目標)バッジで、国連サミットで採択された2030年までに達成すべき17目標を示しています。
例えば、「持続可能な生産・消費の形態を確保する」という目標では、その達成に向けた取り組みの一つに、ごみの発生防止、削減、リサイクル、再利用が求められると規定されています。
私の場合もみなさんと同じように、買い物をする時には袋を持参し、できるだけレジ袋をもらいません。食事をする時にはなるべく割り箸を使わないようにしています。家ではペットボトルや古紙類などは分別して出しています。人間一人の貢献なんて世界全体で見ればわずかなものと思われがちですが、一人一人が努力することで初めて持続可能な大きな目標が達成されるわけです。
地球温暖化がよく問題視されますが、地球環境が正常でなければ、我々人間も生存できません。危機に陥る前に予防対策を真剣に実行しませんか。まずは、SDGsの17目標を意識することから始めるのが肝要です。