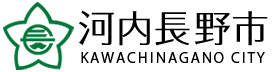本文
河内長野市職員兼業推進条例
河内長野市職員兼業推進条例を制定しました
河内長野市では、社会貢献活動を通じた地域課題の解決、兼業における経験の職務への還元など、市民サービスの向上につながるような市職員の兼業を市として応援するため、河内長野市職員兼業推進条例を制定しました。
| 市の兼業推進について
(1)多様な働き方を認めることにより、職員のウェルビーイングや公務職場の魅力を向上させる。 (2)職員が持つ知識・経験等を地域課題の解決に活用するとともに、兼業を通じて得た経験を職務を通じて地域に還元する。 ⇒上記を、市民サービスの向上につなげていきます。
※ただし、市役所職員は本来の担当業務に全力で取り組むことが大前提であるため、 許可基準を規定した内規を改定し、許可できる事業の類型や兼業で従事可能な時間数を定めるなどしました。 |
地方公務員の兼業制限
地方自治体に勤務する職員は、地方公務員法第38条により営利企業等への従事が制限されており、任命権者の許可がなければ兼業を行うことはできないとされています。地方公務員法において兼業許可が必要とされている趣旨は、公務能率の確保、職務の公正の確保、職員の品位の保持のためです。
| <参考>地方公務員法第38条(一部抜粋) 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 |
国・地方自治体の動向
また、地方公務員の兼業についても、人口減少に伴う人材不足等の背景から、(1)職員の自律的なキャリア形成や自己実現につながるような制度の構築により、公務の魅力を向上させ、人材確保につなげる、(2)公務以外における社会貢献活動で活躍することが期待されています。
河内長野市兼業推進条例
兼業推進の目的
本市では、平成20年6月に兼業の許可基準に関する内規を定めて運用を行ってきましたが、実際に兼業許可の申請が行われる事例は比較的少ないものでした(過去5年間でのべ12件)。なお、これまでに兼業を許可した主なものは、「不動産・駐車場賃貸」、「農業」、「中学校の部活動講師」等です。
この期間中、社会情勢は大きく変化しました。人口減少や高齢化の進展により、地域の担い手不足が進行しており、本市の事業者等についても慢性的に人手が不足しています。本市が抱える地域課題については、市役所だけではなく、地域住民、市内事業者等の皆さまのご協力がなければ解決が難しいのが実情ですが、そのためには、地域の担い手が各地域の課題に取り組むことができるような体制づくりが重要です。
今回の兼業条例制定は、市役所職員が地域で社会貢献活動を行うことにより、地域課題の解決に取り組むことと、職員が兼業を通じて得た知識や経験を市役所に持ち帰り、自らの担当業務で新しいアイデアや企画を生み出すことにより職務へ還元するなど、市民サービスの向上につながるような兼業を市として応援することを目的としています。
また、少子化などの影響により、近年、市役所が行う採用試験の受験者数が減少傾向にあります。本市行政を継続的・安定的に行い、質の高い市民サービスを行うためには、優秀な職員の確保が不可欠です。また、職員の多様な働き方を認めることにより、職員のウェルビーイングや公務に対する魅力を向上させ、現在勤務している職員を含めて、「本市で働きたい」「本市で働き続けたい」と思ってもらえる職場環境づくりを行うことも目的の一つです。職員が能力を十分に発揮することにより、市民サービスの向上につながると考えています。
以上の取り組みを行うことが、本市が職員の兼業を積極的に推進することとした目的です。

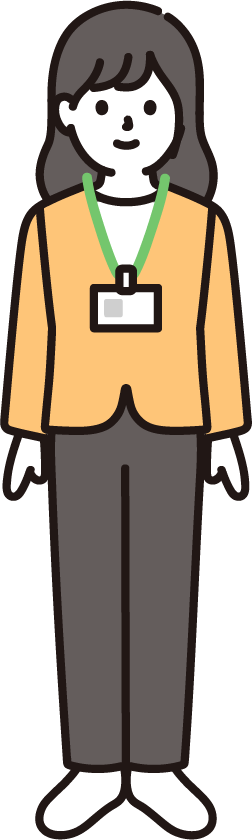
条例制定のねらい
本市では今後、積極的に職員の兼業を推進していきますが、市役所が職員の兼業を許可するに際しては、必ず条例を制定しなければならないものではなく、許可基準などを内規等で定め、基準に照らし合わせて諾否の判断を行うことで十分です。
今回、本市が条例制定を行ったのは、本市が市民サービスの向上につながるような職員の兼業を積極的に推進していくという方針と、市役所が地域の担い手の皆さまと一丸となり地域課題の解決に取り組んでいくという姿勢を市民の皆さまなどにお示しするためです。現在、本市では市役所職員や市民の皆さまの本市への誇りや愛着を醸成するための事業に取り組んでおり、本市の魅力発信や、市民の皆さまが住んでいて良かったと感じていただけるようなまちづくりにつなげていこうとしております。また、職員が兼業の機会を通じて地域に深い関わりを持つことにより、本市の魅力を再発見するなど、住みよいまちづくりに活かすことができると考えています。
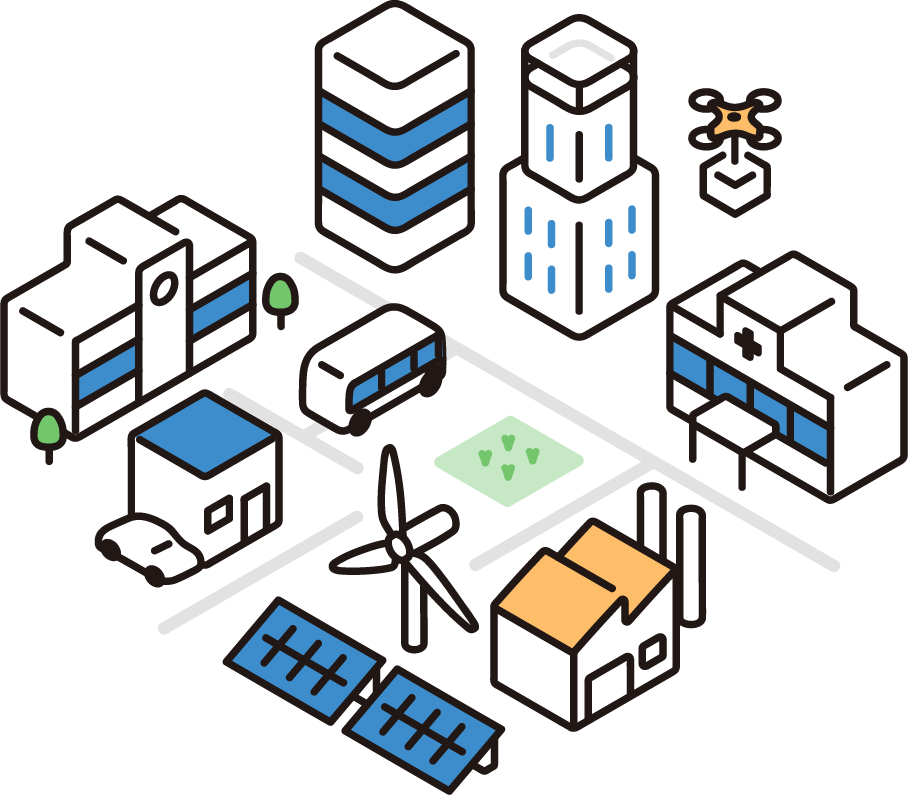
条例の概要
○条例制定の目的(第1条)
条例制定の目的を、「職員が積極的に兼業を行うことを推進することにより地域活動に貢献し、もって市民サービスを充実させること」と定めています。
○兼業推進の基本方針(第3条)
市が行う兼業推進の基本方針を定めています。
職員が兼業を通じて地域課題を解決し、その際の経験を市役所での業務に活用すること、また、職員の多様な働き方を認めることによりウェルビーイングを向上させること、それらの取り組みを通じて市民サービス向上につなげることを市の方針としています。
○兼業の対象となる活動と許可基準(第4条)
職員から兼業の許可申請があった場合、許可できる活動内容や許可基準を定めています。
○市の役割(第5条)
職員の兼業を推進するための市の役割として、「積極的な情報発信の実施等に努める」としています。
兼業の許可基準について
兼業の許可基準を内規で定めています。
(1)営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等に就任する場合
次のすべてに該当する場合
○当該事業に従事することが、公益の増進に寄与するものである場合
○当該事業に従事することによる心身の疲労のため、職員の職務の遂行に支障が生じないこと、又は職務遂行上その能率に悪影響を与えないことが明らかな場合
○その他公務の公平性及び信頼性の確保に支障が生じない場合
(2)不動産又は駐車場の賃貸以外の事業に係る自営を行う場合
次のすべてに該当する場合
○職員の職と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない場合
○職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかである場合
○当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものである場合もしくは(4)に定める活動類型又はそれに準ずる活動を行う場合
○その他公務の公平性及び信頼性の確保に支障が生じない場合
(3)不動産又は駐車場の賃貸
次のすべてに該当する場合
○職員の職と許可に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない場合
○入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかである場合
○その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じない場合
(4)その他
○当該事務又は事務に従事することが、社会貢献活動又は公益の増進に寄与する活動である場合
・職員が自らの知識や経験を活かし、社会貢献活動に従事すること、また、職員が活動で得られた経験を職務遂行や行政サービスの向上に再び活用することを目的とした活動であること。具体的には、以下の活動類型又はそれに準ずる活動(以下は一例を挙げたものであり、以下の事業又は事務に限定するものではない。)であること。
| 活動類型 | 事業又は事務の一例 |
|---|---|
| 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 | 手話通訳者、福祉団体活動、成年後見人 |
| 社会教育の推進を図る活動 | 日本語教室講師、自治体史編纂に係る歴史資料調査 |
| まちづくりの推進を図る活動 | 自治会役員活動、地域イベントのスタッフ |
| 観光の振興を図る活動 | 観光ガイド |
| 農村又は中山間地域の振興を図る活動 | 農作業の補助、林業関連業務の補助、猟友会活動 |
| 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 | 部活動指導員、スポーツ少年団コーチ、登山ガイド、小説の執筆 |
| 環境の保全を図る活動 | 有害鳥獣駆除 |
| 地域安全・災害予防活動 | 予備自衛官、消防団員、防災訓練・講演会等の講師 |
| 子どもの健全育成を図る活動 | PTA役員活動、生活困窮家庭の児童を対象とした学習支援 |
| 地域経済活動の活性化を図る活動 | 地域産業に係る企業への従事(地域活性化につながるもの) |
| その他の公益性の高い地域的、社会的な貢献活動 | 資格試験の監督員、各種研修講師、各種統計調査 |
○職員の職と当該事業又は事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない場合
○当該事業又は事務に従事することによる心身の疲労のため、職員の職務の遂行に支障が生じないこと及び職務遂行上その能率に悪影響を与えないことが明らかな場合
・平日(勤務日)の勤務時間外又は週休日に従事すること。
・兼業先における勤務時間数が週8時間以下、月30時間以下、平日(要勤務日)3時間以下であること。
・原則として週あたり1日以上の週休日を確保すること。
※職員の時間外勤務の状況等についても総合的に勘案し、職員が心身ともに健康な状態で職務を遂行できることを前提とする。
○当該事業又は事務の経営上の責任者でないこと。
○報酬額が社会通念上相当と認められるものであること。
○公務の公平性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
兼業の実績
兼業の実績については、職員のプライバシーに配慮した形で、概要を公開させていただく予定です。