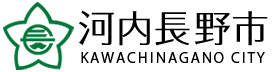本文
広報紙掲載手話コラム~手話で語ろう~(4)
印刷ページ表示
更新日:2022年6月16日更新
広報紙掲載手話コラム ~手話で語ろう~(4)
「手話で国際交流」(令和4年10月号掲載)
「手話で国際交流」
栄町の今村さん
※ろう者= 聴覚に障がいのある人のうち、手話を意思疎通の手段として用いる人
私は生まれつき耳が聞こえません。4歳から毎晩両親と口話(相手の話す内容を口の動きで読み取る方法)の練習をし、また、妹2人の協力もあり、たくさんの言葉を覚えました。
両親のすすめもあり、5歳の時に水泳を始めました。次第に水泳が楽しくなり、もっと頑張りたいと思い練習を積み重ねました。高校1年の冬、デフリンピック(聴覚障がいのオリンピック)の日本代表として出場し、金メダルを獲得しました。本当に嬉しかったのですが、参加者全員が「手話」を使っており、それまで「口話」中心だった私にとっては未知の世界でした。それからろう者の友人と会うことが増え、自然に手話も身につき、口にしなくても思いを伝えることができる「手話」はすごいなと改めて思いました。
デフリンピックには3回出場し、その中で韓国人の方と出会い、お付き合いを始めました。その方も聴覚障がいのため、会話は「手話」で行っていました。同じ手話でも、日本で「久しぶり」は韓国で「別れる」、同様に「好き」は「パンツ」という意味であったりと、両国では4割ぐらい違いもありました。国が違うということで「手話」を含め、様々な壁はありましたが、その方と無事に入籍しました。
今、コロナウィルスの流行によりマスクをしている人が多く、これまで口元を読みとって判断できていたものが、マスクで口元が見えないため何を言っているのか分からず、筆談をすることが増え、急いでいるときは不便に感じています。
息子も難聴なのですが、口話に手話もつけて話し、自然に言葉も覚えるようになってきました。今は楽しく3人で暮らしています。
栄町の今村さん
※ろう者= 聴覚に障がいのある人のうち、手話を意思疎通の手段として用いる人
私は生まれつき耳が聞こえません。4歳から毎晩両親と口話(相手の話す内容を口の動きで読み取る方法)の練習をし、また、妹2人の協力もあり、たくさんの言葉を覚えました。
両親のすすめもあり、5歳の時に水泳を始めました。次第に水泳が楽しくなり、もっと頑張りたいと思い練習を積み重ねました。高校1年の冬、デフリンピック(聴覚障がいのオリンピック)の日本代表として出場し、金メダルを獲得しました。本当に嬉しかったのですが、参加者全員が「手話」を使っており、それまで「口話」中心だった私にとっては未知の世界でした。それからろう者の友人と会うことが増え、自然に手話も身につき、口にしなくても思いを伝えることができる「手話」はすごいなと改めて思いました。
デフリンピックには3回出場し、その中で韓国人の方と出会い、お付き合いを始めました。その方も聴覚障がいのため、会話は「手話」で行っていました。同じ手話でも、日本で「久しぶり」は韓国で「別れる」、同様に「好き」は「パンツ」という意味であったりと、両国では4割ぐらい違いもありました。国が違うということで「手話」を含め、様々な壁はありましたが、その方と無事に入籍しました。
今、コロナウィルスの流行によりマスクをしている人が多く、これまで口元を読みとって判断できていたものが、マスクで口元が見えないため何を言っているのか分からず、筆談をすることが増え、急いでいるときは不便に感じています。
息子も難聴なのですが、口話に手話もつけて話し、自然に言葉も覚えるようになってきました。今は楽しく3人で暮らしています。