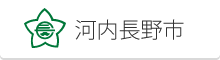本文
河内長野市内を撮影したドローン動画集
印刷ページ表示
更新日:2021年2月10日更新

流谷地区「蝋梅の里」
天見駅の西、八幡神社を通り過ぎ、看板のある角を曲がると、蝋梅(ろうばい)の花で黄色く染まった里山が広がっています。
空から見た流谷地区「蝋梅の里」<外部リンク>
天野谷
金剛寺の中心伽藍周辺に広がっていた子院群。かつて寺領だった天野谷の里山景観とともに、中世の面影を残しています。
天野山金剛寺
金堂や多宝塔など多くの建造物は、戦乱を生き抜いた金剛寺の歴史を語る証人といえるでしょう。
観心寺
一山寺院と呼ばれる景観が分かります。
観心寺七郷(鳩原など)
自然の地形を生かした棚田やあぜ道など、中世を思わせる風景が続きます。
石仏城跡
楠木正成が築城した支城の一つで、天見合戦の際に、兵を伏せたという伝承が残っています。現在も城郭遺構の一部が残っていますが、これは戦国時代のものと見られています。
矢伏観音
石造十一面観音で高さ43cm幅 18cmの船形石に刻まれており、楠木正成にまつわる「身替わり」伝説が伝えられている。幼少の頃の正成が兵法家大江時親に兵法を学んでいた際に、楠木氏と敵対する八尾(矢尾)顕幸が刺客を放ち命をねらわせたが、観音の加護により命を救われたとされる。幼少期の正成の逸話を後世に伝える舞台となっている。
楠公通学橋
楠公通学橋は、楠木正成が、観心寺から大江時親邸に通うために渡った伝えられる橋です。近代に創作された逸話と考えられますが、正成顕彰の活発さが伺えます。
天野山金剛寺
天野山金剛寺は、楠木正成の自筆書状などが伝わっており、彼の人柄などを知る事のできる貴重な資料が多く収蔵されている寺院で、観心寺と同じく中世の教育機関となり、南朝方の拠点となりました。