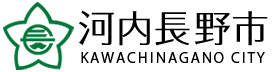本文
国民年金の制度について
加入する人
必ず加入しなければならない人
- 第1号被保険者 国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業者・学生など
- 第2号被保険者 厚生年金被保険者・共済組合加入者(老齢厚生年金等を受けられる65歳以上の人は除く)
- 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人
希望すれば加入できる人(任意加入制度)
1. 日本国籍を有し、海外に居住する20歳以上65歳未満の人
2. 次の4つの条件をすべて満たす人
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
- 厚生年金保険・共済組合等に加入していない人
※年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人は受給権を満たすまで加入できます。(昭和40年4月1日以前生まれの人のみ)
※任意加入は、手続きをした月分から保険料を納付することができます。
こんなときには届け出を
- 会社を退職したとき(扶養されている配偶者も手続きが必要です)
- 配偶者の扶養からはずれたとき
- 海外からの転入、海外への転出をするとき
- 任意加入するとき・やめるとき
- 3号被保険者の配偶者が65歳になったとき
付加保険料について
第1号被保険者が申し出ることによって納付できる保険料のことです。申し出をした月分から納付することができます。付加保険料は月額400円で、定額保険料に加えて納付します。
なお、国民年金保険料の免除・納付猶予・学生特例などの承認を受けている人、国民年金基金に加入している人は付加保険料を納付することはできません。(産前産後免除を除く)
日本年金機構HP 年金加入についてはこちら<外部リンク>
年金の給付
老齢基礎年金
受給資格期間が10年以上ある人が65歳になったときに支給
障害基礎年金
国民年金加入中や20歳前の未加入期間に初診日のある病気やけがで国民年金法で定める障がい等級1級または2級に該当したときに支給
※一定の要件あり
※60歳から65歳の未加入期間に初診日があるときも対象となる場合あり
遺族基礎年金
一定の保険料を納めた人や老齢基礎年金を受けられる資格期間のある人が死亡したとき支給 (資格・納付要件あり)
受けられる人
・ 死亡した人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」
・ 死亡した人によって生計を維持されていた「子」
特別障害給付金
平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生または昭和61年3月以前に厚生年金保険に加入していた人の配偶者で、任意加入していなかった期間中の傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1級・2級の状態にある人に支給(ただし他の年金との重複受給不可、本人の所得制限あり)
日本年金機構HP 年金受給についてはこちら<外部リンク>
第1号被保険者独自の給付
付加年金
付加保険料を納めた人が老齢基礎年金の受給権を得たとき支給
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数の合計が3年(36月)以上ある人が何の年金も受けずに死亡したとき、生計を同一にしていた遺族に支給(要件あり)
※寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられるときは、支給を受ける人の選択によってどちらかが支給されます。
日本年金機構HP 国民年金独自給付についてはこちら<外部リンク>
保険料の納付
第1号被保険者の毎月の保険料は、年度ごとに決定されます。保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末(末日が休日等の場合は翌営業日)です。納付期限より2年以内であれば納付できますが、2年を過ぎると時効により納付できなくなります。
納付の方法
日本年金機構から送付される納付書を使用するときは、次の種類があります。
・金融機関、郵便局で納付する
・コンビニエンスストアで納付する
・電子納付(Pay-easy)で納付する
・スマートフォンアプリで納付する(令和5年2月20日より)
口座振替のときは、金融機関、郵便局(簡易郵便局を除く)または、天王寺年金事務所で手続きして下さい。引落方法は早割(当月納付)、毎月納付、6ヶ月前納、1年前納、2年前納があります。
クレジットカード納付のときは、申込書に必要事項を記入のうえ、天王寺年金事務所へ送付してください。引落方法は毎月納付、6ヶ月前納、1年前納、2年前納があります。
早割・前納により納付されるときは、割引があります。
日本年金機構HP くわしい納付方法等についてはこちら<外部リンク>
保険料の免除
産前産後免除 (平成31年4月から)
第1号被保険者が出産するとき、届出により出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が全額免除されます。多胎妊娠のときは、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が全額免除されます。
*出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された場合を含みます。)
*この免除期間は、年金受給額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。
*この制度の対象は国民年金1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人です。
*国民年金 育児保険料免除(令和8年10月予定)
法定免除
第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するとき、届出により保険料が全額免除されます。
(1)障害基礎年金などの2級以上の公的年金の受給権者であるとき。
(2)生活保護法による「生活扶助」を受給しているとき。
(3)厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所しているとき。
申請免除
保険料を納めるのが困難なとき、第1号被保険者が申請し、本人・配偶者及び世帯主の所得状況により承認されると保険料が全部または一部が免除されます。申請免除には、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4種類があります。
*過去の期間については、申請月の2年1ヶ月前分までさかのぼって申請できます。
*学生の方は、学生納付特例の制度を利用ください。
納付猶予
保険料を納めるのが困難なとき、20歳以上50歳(平成28年6月までは30歳)未満の第1号被保険者が申請し、本人及び配偶者の所得状況により承認されると保険料の納付が猶予されます。
*過去の期間については、申請月の2年1ヶ月前分までさかのぼって申請できます。
*納付猶予期間は、将来の年金を受けるための資格期間には含まれますが、受け取る年金額の計算には算入されません。
*学生の方は、学生納付特例の制度を利用ください。
学生納付特例
20歳以上の学生である第1号被保険者が申請し、本人の所得状況により承認されると保険料の納付が猶予されます。
*学生納付特例期間は、将来の年金を受けるための資格期間には含まれますが、受け取る年金額の計算には算入されません。
*学生とは、高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院・専修学校・各種学校その他(要件あり)に在学する人です。(夜間・定時制課程・通信課程も含まれます。)
日本年金機構HP 保険料免除申請等についてはこちら<外部リンク>
追納制度
法定免除・申請免除・納付猶予・学生納付特例の期間については、老齢基礎年金の年金額の減額の対象になります。本人の申出により、承認された月の前10年以内の期間であれば、保険料を全部または一部を納付することができます。追納することにより満額の老齢基礎年金に近づけることができます。
*追納は原則先に経過した期間から順次納付します。ただし、納付猶予・学生納付特例の期間については優先できるときがあります。
*追納する保険料には、経過期間に応じて決められた額が加算されます。なお、免除された月の属する年度の翌々年度以内に追納するときは加算がつきません。
日本年金機構HP 追納制度についてはこちら<外部リンク>
年金ポータルサイト
公的年金及び私的年金の制度や手続きについて、関係機関のウェブサイト 等に掲載された情報を誰でも容易に探せるよう、年金ポータルサイトが開設されました。下記のバナーをクリックしてご利用ください。
問い合わせ先
市民窓口課(年金担当) または 天王寺年金事務所 06-6772-7531
ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004 (050で始まる電話の場合 03-6630-2525)