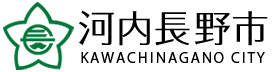本文
大阪・関西万博「地域の魅力発見ツアー」みなはれゾーンへの出展について
中世が「好き。」歴史でつながる河内長野
河内長野市には、日本を代表する歴史・文化の魅力が存在しています。特に中世の文化遺産は、非常に充実しています。大阪・関西万博では、2025年5月9日(金曜日)から11日(日曜日)にかけて開催される「地域の魅力発見ツアー~大阪43市町村の見どころ~」で観心寺、金剛寺、烏帽子形城跡の3つの中世の史跡をとりあげ、その魅力を世界に発信します。
観心寺
観心寺は市域の北東部にあり、飛鳥時代に役行者によって雲心寺として創られました。その後、弘法大師空海の命で、その弟子の実恵や真紹によって観心寺として整備が進められました。また、朝廷が公認する寺院となり、承和3年(836)に朝廷より周囲に領地が与えられました。これによって、観心寺が、中世を通じて領地の経営、支配を行うことになりました。
現在の観心寺境内には、国宝の金堂、重要文化財の建掛塔、訶梨帝母天堂などの建物があります。しかし、かつての境内には、南向きの山の斜面にさらに多くのお堂や子院がありました。万博では、この様子を復元した境内模型の展示を行います。
観心寺は中世を通じて周囲の荘園を支配していました。荘園とは私有地のことを意味します。しかし、現代的な意味での私有地とは異なっていました。荘園は奈良時代から戦国時代にかけて、少しずつ形を変えながらも存在しました。荘園を基盤とした社会の仕組みは荘園制といわれ、日本の中世社会を支えました。観心寺の古文書からは、荘園制が遷り変っていく様子が分かり、万博では古文書のレプリカを展示します。
金剛寺
金剛寺は河内長野市域の南西部にあり、奈良時代に行基が草創したと伝えられています。その後、平安時代末に阿観によって整備されました。金剛寺の場合は、周囲に勢力を張っていた武士である源貞弘が開発した耕作地が寺に寄進されたことで、周囲に領地が形成されました。中世の天野山金剛寺は、単なる宗教施設ではなく、都市的な景観と機能を持っており、領地を統治する行政機関でもありました。このほか、高等教育機関や軍事施設としての機能も併せ持っていました。伽藍と呼ばれる境内の中心部は、ひときわ高い築地塀に囲まれており、内部には巨大な建物があり、塔がそびえています。伽藍は、祭礼を行う場であるとともに、学問研鑽を行う場、政治の場でもありました。伽藍の周囲には、子院とよばれる付属寺院群が幾重にも取り巻いています。子院は戦国時代に100坊近くありました。
金剛寺は、和泉道によって当時の貿易港であった堺や、高野山にも連絡しています。主要な交通ルートを抑えており、様々な物資が行き交いました。このことを示す出土遺物の展示も行います。
境内全体は、小高い丘陵や土塁に囲まれており、谷の入り口は、門と土塀で閉鎖されています。このような事から金剛寺は難攻不落の城塞都市ともよべるものでした。この様子を伝える境内の模型を万博で展示します。
烏帽子形城跡
烏帽子形城は、室町時代の後半に河内を統治した大名の畠山氏によって築かれました。その後、新たに畿内地域に進出してきた三好氏、織田氏、豊臣氏によっても使われました。 城内には、巨大な土塁、迫力ある横堀などが巡らされており、この様子を迫力ある模型で展示します。城の中心部である主郭からは、大阪平野全体が望め、この中には、多くの山城、交通の要衝などを見渡すことができます。