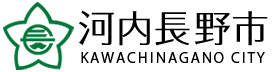本文
国史跡金剛寺境内 鎮守橋の整備について
令和6年9月から、国史跡金剛寺境内の重要な構成要素である鎮守橋(国登録有形文化財)について、木材等に傷みが目立つようになってきたことから、国・市の補助金を活用し、史跡整備事業(保存修理)を実施しています。
令和6年度は天野川(西除川)石垣の3次元測量、令和7年度は天野川(西除川)石垣の3次元測量・鎮守橋とその基部の石垣の解体、令和8年度は鎮守橋と石垣の復旧を予定しています。
金剛寺鎮守橋の概要
この建造物は、天野山金剛寺境内を南北方向に流れる天野川(西除川)にかかる7つの橋のひとつで、金堂などのある主伽藍と鎮守社(丹生・高野明神社、水分明神社)を結ぶ重要な橋で、橋桁がわずかに反りを持ち、上部に覆屋(おおいや)がつく木造廊橋(ろうきょう)です。
覆屋は、橋本体とは独立した柱によって支えられており、その規模は、桁行3間、梁間1間(全長6.4m、幅2.5m)で、切妻造で銅板葺となっています。
現在の鎮守橋と覆屋は、慶長時代の旧形を保ちつつ、昭和16年に再建されたものですが、主伽藍と鎮守社を結ぶ重要な橋であり、金剛寺の往時の寺観を現在に伝える貴重な建造物であるとして、国登録有形文化財になっています。
史跡整備、文化財建造物の保存修理について
史跡整備は、史跡の保存と活用を図ることを目的として実施するものです。天野山金剛寺では、『史跡金剛寺境内保存活用計画』を策定し、これに基づき、景観や地下遺構が損なわれないように史跡の維持管理、保存活用を行っています。
天野山金剛寺は、史跡の構成要素である建造物の多くが重要文化財等に指定されている点に特徴があります。文化財建造物は、地域の歴史や文化を今に伝える貴重な財産ですが、多くの建造物は常に風雨や雪等にさらされており、損傷や老朽化を避けられません。適切な時期に保存修理を行い、それを繰り返すことによって、より良い状態で後世に伝えていくことができます。