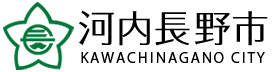本文
きょうだい喧嘩が絶えません。小さい子の方をかばってしまうのが気にいらないようです。
答え
きょうだいがいるからこそ、喧嘩ができるのです。
1番身近なきょうだいと喧嘩することは、小さくても厳しい世界で生きている子どもにとって、様々な問題を乗り越えるために、日々練習を重ねているということでもあり、人と人との関わり方を知らず知らずのうちに学んでいることにも繋がります。
つまり、子どもは喧嘩で多くのことを学んでいるので、できれば止めに入らないほうが良いと思います。
子どもにも体力の限界があるので、いつまでも喧嘩をし続けていることはありませんし、放っておいても彼らなりのルールがあるので、いつの間にか仲直りしていることもあります。
しかし、ある程度やりあったなと思った頃、喧嘩の仲裁をするというよりは、何か違う方法で『休止』という形で持っていくと、あっさり喧嘩が終わることもあります。
例えば、「お母さんお菓子食べるけど、一緒に食べる?」と言った風に声をかけると、コロッと忘れて飛んでくることもあります。
また、理由も聞いていない内に、ついつい下の子をかばってしまうと、「お母さんは下の子ばかり可愛がる」と、子どもにとって大きな心の傷になることがあります。
親から受ける愛情の比率は子どもにとっても重大な問題です。それが偏っていると感じたとき、子どもは私たちが思う以上に、(強烈な)ダメージを受けてしまいます。
そのため、喧嘩のジャッジをしなければいけない場合は『引き分け』とし、子どもの興奮が収まった頃に時間を見計らって、子ども1人ずつそれぞれに、ジャッジの結果を伝えるのが効果的と言われています。また、その時にどうして『引き分けなのか』ということをきちんと話すことで、子どもはより納得することができます。
基本的に、あまり親が介入しないのが喧嘩の対処法ですが、喧嘩から子どもの危険信号が出ている場合もあります。きょうだい喧嘩で明らかにいつもと違う場面が出てきた場合は、子どもの何かしらの『SOS』を出しているケースが多くあります。普段はすぐに収まる喧嘩が長引いていたり、口喧嘩などで済むようなシーンでも暴力的になっている時などです。そういう場合、子どもがストレスを感じていたり、いらいら感があったり、何か問題を抱えている可能性があります。このときは、八つ当たりされた子どもにフォローを入れながら、問題が起きている子どもの信号を優先して受け止めてあげる必要があります。時間をかけて話を聞いてあげてください。
学童期に入り、外で過ごす時間が多くなるにつれ、子どもの『SOS』の出し方は多様化していきます。大きくなってきた時こそ、親の支援が必要な場合があるので、異変に気付いた時は、時間を取って話し合いの場を設けた方がいいと考えられます。
子どもたちのきょうだい喧嘩を見ていると、危ないくらいの取っ組み合いに発展するケースもありますし、言葉の暴力も聴いていると、なかなか辛辣なものがあります。けれども、取っ組み合いの喧嘩では身体の痛みを知り、力加減を覚え、口喧嘩では言葉ひとつでも心に大きな傷を負うことをお互いに知り、同時に優しさも学んでいきます。
すべてが子ども任せではなく、すべてに親が口を挟むのではなく、「ここぞ!」という時に手を差し伸べ、援助をすることが大切になってくるのではないでしょうか。