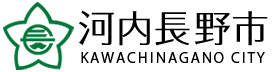本文
『ADHD(注意欠如多動症)』について、教えて下さい。
答え
「この子は『ADHD(注意欠如多動症)』ではないか」という心配…
- エネルギーが高く元気で活発な子
- 先生や保護者の指示とは違う言動を取ってしまう子
- お友達とうまく関わるのが苦手な子
など家族にとって、1度は頭をよぎる心配であると思います。
アンバランスな発達の一つである『ADHD』の子どもは…
『不注意』
- 細かいところに注意が払えずケアレスミスが多い
- 忘れ物や物をなくすことが多い
- 指示に従えなかったり、課題をやり遂げられない
など
『多動性』
- そわそわする
- 席を離れて立ち歩く
といった活動の多さ。
『衝動性』
- 順番を待てない
- 我慢ができない
- 注意がそれやすい
- 忘れ物が多い
など
『注意集中の難しさ』、といった特徴が見られます。加えて、『感情のコントロールの難しさ』を見せる子どももいます。
子どもが『ADHD』であるのか?、他の発達の問題があるのか?、という診断は医療機関でなされます。
相談機関では、このような子どもをどのように理解し、家族として対応していくかを考えていきます。
『ADHD』の特徴を持つ子どもの多くが抱える深刻な問題は、『自己評価の低さ』です。
周囲からいつも、「わがまま」・「自分勝手」・「トラブルメーカー」と見られている子どもは、とても傷つくことに加えて、その否定的な評価を取り入れてしまいます。
そして、反発するように一層派手な行動を取ってしまい、周囲との間に溝が出来てしまいます。このような悪循環を防ぐためにも、周囲の理解は非常に重要です。注意したことに対して、「やらない・しない」のではなく、『できない』というその子の苦手さを理解した上で、子どもの『できない悔しさ・つらさ』に寄り添った関わり合いが、子どもの心の健康には大切です。
その上で、子どものできないを『できる』に近づけるためには、どのような周囲の手助けが必要か、「家族」・「学校場面」・「相談機関」で考え、実践していくことで、子どもは自信を持ち、周囲とうまく関わることにつながります。
例えば、感情のコントロールが苦手な子どもには、
- 深呼吸
- 数字を数える
- その場を離れる
などで気持ちを落ち着けることで、気持ちの切り替えができるようになるなどがあります。
何よりも、子どもも保護者の方も1人で悩まず、まずは相談する環境を作ることが大切です。