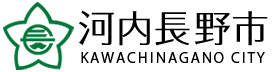本文
市指定 木製密教法具
印刷ページ表示
更新日:2019年4月17日更新
区分(有形文化財)種別(工芸品)指定番号(工5)
市指定文化財 木製密教法具
mokusei-mikkyou-hougu 一式
| 所在地 | 河内長野市天野町 |
|---|---|
| 所有者 | 天野山金剛寺 |
| 時代 | 室町~江戸 |
| 指定年月日 | 平成16年12月2日 |

「密教法具」は金属製のものが一般的であるが、天野山金剛寺の求聞持堂には、かつて堂内で使用されていたとされる木製の密教法具が伝えられている。
| 器種名称 | 点数 | 備考 |
|---|---|---|
| 二器蓋 | 2点 | 針葉樹(カヤか) |
| 六器・二器 | 15点 | 針葉樹(カヤか) |
| 花垸(台皿) | 13点 | 針葉樹(カヤか) |
| 飲食器 | 5点 | 針葉樹(カヤか) |
| 五鈷鈴 | 1点 | 針葉樹(カヤか) |
| 金剛盤 | 1点 | 針葉樹(ヒノキか) 「日野観音寺乾坊」の墨書あり |
| 柄香炉 | 1点 | 不明(但し、柄部はタケ) |
|
合計 |
38点 |
本法具のような木製のものの報告例はごく乏しいのが現状で、制作年代の基準作を求めることは困難であるが、本法具類には金属器加工と同じ製作跡が認められることから、各法具の形式を金属器の形式にて判断することは可能である。
それによると、六器・二器、飲食器、金剛盤、五鈷鈴(鈴身部)が14世紀、花垸(台皿)が15世紀から16世紀、柄香炉は形式が退化・省略化されているため江戸時代まで降るものと考えられる。
このような密教法具が一式で現存している報告例は、全国的には宝生寺蔵の「木造密教法具」(横浜市指定文化財)の一例が知られているのみである。
以上のことから、この密教法具は、河内長野市の中世から近世にかけての密教寺院に於ける密教法具のあり方が窺え、また全国的にも希少な宗教遺産として貴重である。