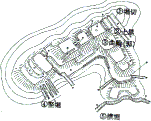プログラム
1.報告:烏帽子形城の概要と発掘調査成果
河内長野市教育委員会職員
太田宏明
2.講演:古記録からみた烏帽子形城
河内長野市文化財専門委員会委員
堀内和明氏
3.講演:考古学からみた中世
~村落遺跡をとおして~
国立歴史民俗博物館・総合研究
大学院大学教授
広瀬和雄氏
4.シンポジウム「中世社会と烏帽子形城」 |

教育長のあいさつ |

講演を聴く参加者 |
烏帽子形城の概要と発掘調査成果の報告
(配布資料より)
主郭をめぐる巨大な横堀・土塁は周辺の山城の城郭ではみられない規模であり、地域内で発展したものでない。一方、織田信長や豊臣秀吉が築城した山城に近い規模の横堀や土塁である。
豊臣秀吉の根来攻めの際に改修されて、現在に至っているものと考えられるので、この改修当時の遺構が今多く残っていると考えられる。
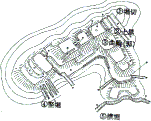
(山城模式図-配布資料より) |
古記録からみた烏帽子形城(配布資料抜粋)
①烏帽子形城の初見史料
「中臣祐雑記」大永4年(1524年)9月~12月条
②「押子形城」は「烏帽子形城」の前身
「経覚私要鈔」文正元年(1466年)9月4日条
③三好三人衆、畠山高政の「烏帽子形城」を攻略
「言継卿記」元亀元年(1570)10月22日条
④「烏帽子形城主」草部房綱、金剛寺に兵糧・築城資材の提出を命じる。
永禄(1558~70年)カ11月19日草部房綱書状「金剛寺文章」
⑤・・・・・・・・・・・・・・・ |

講演を聴く沢山の参加者 |

シンポジウムの模様 |
考古学からみた中世(配付資料から抜粋)
~村落遺跡をとおして~
①中世前期の村落
10世紀後半以降、A・B・C型の散村が一般化してくる。
A型:小型の建物が2~3棟まとまって1つの村落をつくる。
B型:中型の床張り建物(40~60㎡)に小型の建物(納屋か)が付属する。
C型:大形建物を主屋に、中小の建物群が数棟伴う。
②中世後期の村落
畿内地方では、14世紀頃から集村-溝で区画された多数の宅地-が形成される。
集村A型→集村B型へ
③領主居館の成立:12世紀末頃に出現・・・・ |
シンポジウム(要約)
河内長野における中世は平安後期、概ね鳥羽上皇が高野山詣を行ったあたりの時期から中世の歴史がはじまる。
烏帽子形城の特徴は、
①立地条件に最適な場所に築城されている。
②山城であるのにかかわらず城内が長方形に整地されている。
③巨大な横堀を備えている。
④他の山城に先駆けて瓦葺きであった(瓦葺きの意味、瓦の製作年代の考察が今後の課題)。
⑤居城ではなく戦闘の城である。
これからは・・・
①総合報告書の作成
②国史跡としての指定へ
③山城らしく整備し、河内長野のシンボル化、活用へ
里山としての自然保護とのバランスを図りながら
④河内長野市のキャッチフレーズ「都市と共生している中世城郭」の提言
⑤平成22年10月22日(金)午後1時30分~3時、模擬合戦「烏帽子形城 秋の陣」を開催
市長が畠山領主になり、手作りの甲冑を着た三日市小学校5年生が畠山軍、阪南大学学生
が三好軍となっての烏帽子形城の攻防をくりひろげます。
|
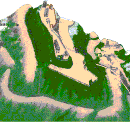 喜多町と上田町にまたがって烏帽子形公園があります。この中には中世につくられた山城・烏帽子形城跡があり、今でも巨大な空堀や土塁が残っていて見ることができます。この城は応仁の乱以降に畿内でくり返された内乱の舞台として歴史に何度も登場します。特に、分裂した河内守護・畠山氏の激闘、豊臣秀吉による紀伊根来衆攻めの戦略上の重要拠点となりました。またキリシタン大名が城を守ったことが宣教師ルイス・フロイスによりヨーロッパに紹介されました(資料より)。この烏帽子形城がつくられた中世社会とはどういう時代だったか、烏帽子形城はどのような城であったのかを講演とシンポジウムで明らかにしようとするこころみでありました。
(烏帽子形城復元予想図-配付資料を着色)
喜多町と上田町にまたがって烏帽子形公園があります。この中には中世につくられた山城・烏帽子形城跡があり、今でも巨大な空堀や土塁が残っていて見ることができます。この城は応仁の乱以降に畿内でくり返された内乱の舞台として歴史に何度も登場します。特に、分裂した河内守護・畠山氏の激闘、豊臣秀吉による紀伊根来衆攻めの戦略上の重要拠点となりました。またキリシタン大名が城を守ったことが宣教師ルイス・フロイスによりヨーロッパに紹介されました(資料より)。この烏帽子形城がつくられた中世社会とはどういう時代だったか、烏帽子形城はどのような城であったのかを講演とシンポジウムで明らかにしようとするこころみでありました。
(烏帽子形城復元予想図-配付資料を着色)